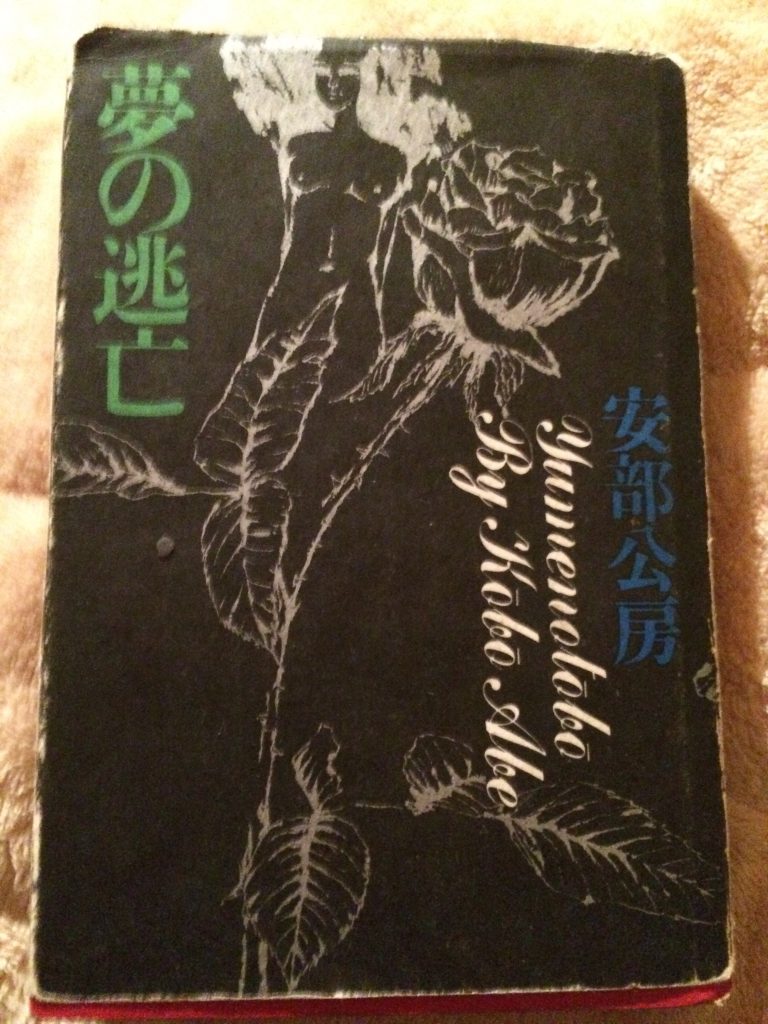この前の土曜日、ジャズライブを見に行った。心身から湧き上がる音とガラス戸の向こうの緑とあたたかな古い電球。もう三日も前のことなのに、うまく感想を言うことができない。本当に好きなものの理由は言えない。ドラムの後ろに荒野に沈む夕日が見え、佐藤さんの汗が見え、ああ、本当によかった。
別にドラムの音がなくたって生きていける。本がなくても、絵画がなくても。しかし、意味のあることだけを詰め込んだ毎日は考えるだけで息が詰まる。小学生のころの私を生かしたのは、図書館だった。おもいだせば恵まれた少女時代、しかしなにかに押しつぶされそうだった。
ハイカルチャーでなくとも、サブカルと呼ばれるものでなくとも、あやとりや、おばあちゃんたちの歌のような、根付く遊びや余白そのものが尊い。畳に寝そべり、日差しの中光る埃をじっと見ていたこと。ひたすらにブランコをこぐこと。年に何回か、お墓の前でご飯を食べること。艶やかな泥団子をひとりつくったこと。土砂降りの庭でずぶ濡れになったこと。それらの先に文化や芸術があると信じてやまない。
恵那では昔、多くの家でおかいこさんを飼っていたと聞く。その白い糸を絹とするとき、綿花から一本の綿を紡ぐとき、きっと彼女たちは歌を歌ったんじゃないか、と夢想する。一体どんな歌をうたったのだろう。朝早く起きて寒空の下で、煮炊きをしながら歌う歌をいちばんに聞きたいとおもう。
大文字の歴史からこぼれ落ちていく、小さな文化の小さな空白。無駄、と呼ばれるもの。文化、と呼ばれるもの。ご飯があるから体が動く。家があるから眠れる。空白があるから生きていける。