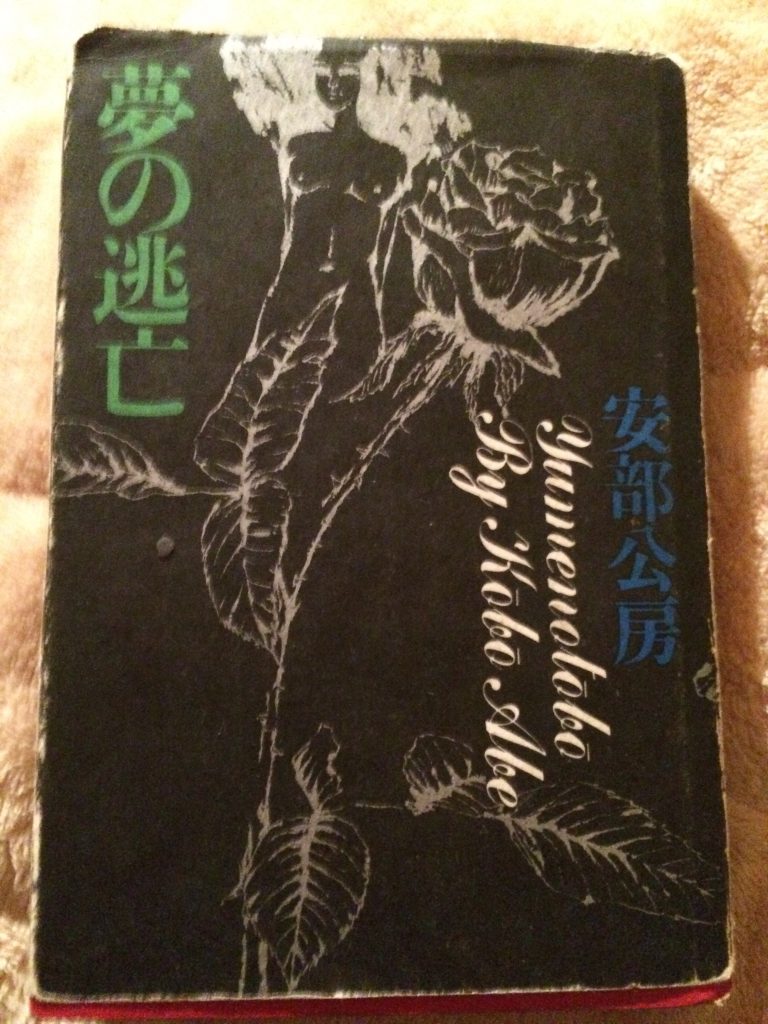岐阜新聞の素描欄にて2018年9月~10月の毎週土曜日、全9回で掲載された庭文庫店主百瀬実希の文章を紹介します。

白い紙に黒いインクで書かれた文字がどうして知らない世界に連れて行ってくれるんだろう。それは、小さな頃からの疑問であった。
十九歳まで沖縄で育った。その頃からドッジボールをすることや、ご飯を食べることと同じくらいに、本を読むことが好きだった。ランドセルに図書館で借りた本を入れて帰るとき、いつもうきうきした。ページを開くとまわりの音も色も消えて、いつのまにか本の世界に入って行く。知らない世界、見たことのない場所、貪るように本を読んでいた。同じ本を飽きずに何度も読んだ。何回読んでもいつも本の世界は新しくて、本当に同じ本なのだろうかと疑ったこともあった。
女の子だから、お姉ちゃんだから、優等生だから、勉強ができないから、かわいくないから、走るのが早いから、そんなことには全く関係ない本の世界の扉がいつも開いていることが、わたしを支えた。常に本は灯火であり、心の錨であり、風穴であった。
あの頃より大人になった。あの頃ほど、本を必要としなくなった。たくさん読むことよりも、毎年一冊でも心の底に響く本に出会えれば満足するようになった。無性に遠くに行きたくなった時には、本棚を眺める。何気なく手に取った本を読み終わる頃には、すこしだけ息がしやすくなっている。本は、大人になった今でも、遠くへ行くための乗り物だ。
すべての人が、本を読むべき、なんて思わない。読まなくて済む人は、読まなくてもいいのだ。ただ、もし無性に息苦しい人、遠くへ行って見たいと思う人、そんな人は試しに本屋さんに行ってみるといいと思う。
そんな本と出会える場を、恵那市という小さな街にもつくりたくなった。そうして田舎の古本屋「庭文庫」は始まった。
◎他の記事はこちら
【素描第一回】本は新しい世界への扉
【素描第二回】幼き日の羅針盤『精霊の守り人』
【素描第三回】たったひとつの『声』
【素描第四回】岐阜に移住したときのこと
【素描第五回】無職の側には美しい山と稲穂があった
【素描第六回】好きなことを仕事にしたいわけではなかった
【素描第七回】出張古本屋として活動していた頃のこと
【素描第八回】生きにくかったあの頃の私へ
【素描第九回】理想郷なんてどこにもないから