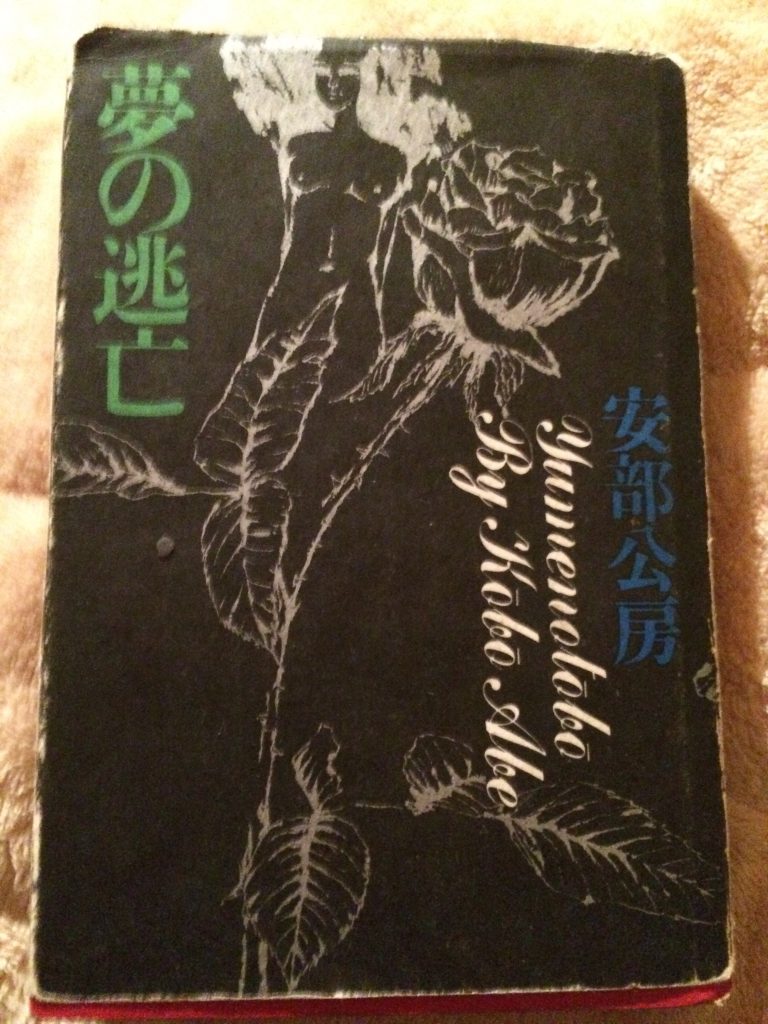岐阜新聞の素描欄にて2018年9月~10月の毎週土曜日、全9回で掲載された庭文庫店主百瀬実希の文章を紹介します。

強い女の子になりたかった。毎晩リレーの練習をしたり、男の子に混じってサッカーをした。どれだけ体を動かしても、なんてことない平凡な小学生であることは、頭のどこかでわかっていた。
上橋菜穂子著『精霊の守り人』の主人公、女用心棒バルサはあの頃の憧れであった。父を殺され故郷を追われたバルサは、ひょんなことから幼い王子の命を救い、一緒に旅をすることになる。目に見える世界と目に見えない世界の交錯する物語のなかで、彼女はいつも強かった。喧嘩が強い、ということだけではない。乾いた諦念のようなものを持ちながら、いつだって大事なものを離さずに旅をするバルサの姿を見ているだけで、自分もいつかそうなれそうな気がしていた。
あんなに何度も繰り返し読んだ本なのに内容はすっかり忘れてしまった。ただしなやかな一本の芯に貫かれるバルサの立ち姿だけが目に浮かぶ。おばさんだと思っていた彼女の年齢は30歳で、私も同じような歳になった。
思い描いていた大人にはなれなかった。相変わらず打たれ弱く、面倒くさがりで、怠惰だ。それでも大事な物を手離さず生きてこられたのは、幼き日の私の側にバルサがいたからだ。読み返すたびに、自分の中に芽吹いている当たり前がこの本によって生み出されたことをまざまざと知る。もし愛読書が別の本であったら、別の人生を歩んでいただろう。
全てが新しかったあの目線を再び取り戻すことはできないけれど、たまにバルサに会いに行く。今よりもずっと空が高かった時のこと、ずっと忘れたくないと思う。


◎他の記事はこちら
【素描第一回】本は新しい世界への扉
【素描第二回】幼き日の羅針盤『精霊の守り人』
【素描第三回】たったひとつの『声』
【素描第四回】岐阜に移住したときのこと
【素描第五回】無職の側には美しい山と稲穂があった
【素描第六回】好きなことを仕事にしたいわけではなかった
【素描第七回】出張古本屋として活動していた頃のこと
【素描第八回】生きにくかったあの頃の私へ
【素描第九回】理想郷なんてどこにもないから