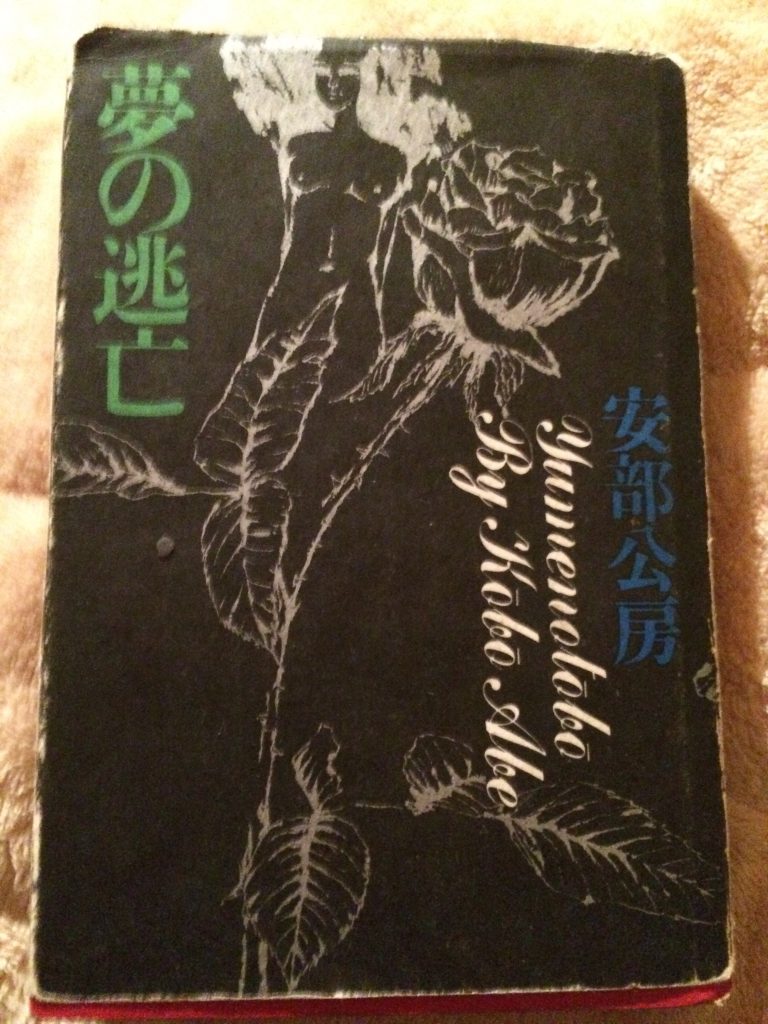ラベリングという単語を知ったのは、大学生のときだった。「〇〇ちゃんて××よね」とその人に見えないラベルを貼ってしまうことをラベリングという。それがネガティブなものであれば、ポジティブなものであれ、私たちはそれらに苦しめられていること知った。
たったひとりの誰か、たったひとつの何か、と私たちは対峙することができるだろうか。あの人は障害者だから、あの子は女の子だから、ここは田舎だから、果てしないラベリングが今日もそこここで行われている。
齋藤陽道著『声めぐり』は、たったひとつの声と、たったひとりの人と会い続けて行くことを大切にした彼の半生が描かれていた。苦いことも、恥ずかしいことも含めて書かれていた。彼は耳が聞こえない写真家だ。耳の聞こえない彼が声に出会う、ということは一見不思議なことに思える。しかし、声とは口から発される言葉だけを指すのではない。
ラベルを貼るのは簡単だ。自分の知っている枠に相手を押し込んで、わかった気持ちになる。安易で、インスタントで、傲慢だ。ラベルを剥がしていくことは、その人としてその人を見ることに他ならない。どうすれば、そんな風にできるのだろう。私はずっとわからなかった。
誰かの体温や眼差し、ふるまい、小さな口の動き、ふんわりとカーテンを撫でる風、陽光。そういったものはすべて声だ、と齋藤さんは言う。そのたったひとつの声と出会っていくことが私にもできるだろうか。いつか、誰かにラベルを貼らなくなった日、私は自分に貼られたラベルからも自由になれる。
◎他の記事はこちら
【素描第一回】本は新しい世界への扉
【素描第二回】幼き日の羅針盤『精霊の守り人』
【素描第三回】たったひとつの『声』
【素描第四回】岐阜に移住したときのこと
【素描第五回】無職の側には美しい山と稲穂があった
【素描第六回】好きなことを仕事にしたいわけではなかった
【素描第七回】出張古本屋として活動していた頃のこと
【素描第八回】生きにくかったあの頃の私へ
【素描第九回】理想郷なんてどこにもないから