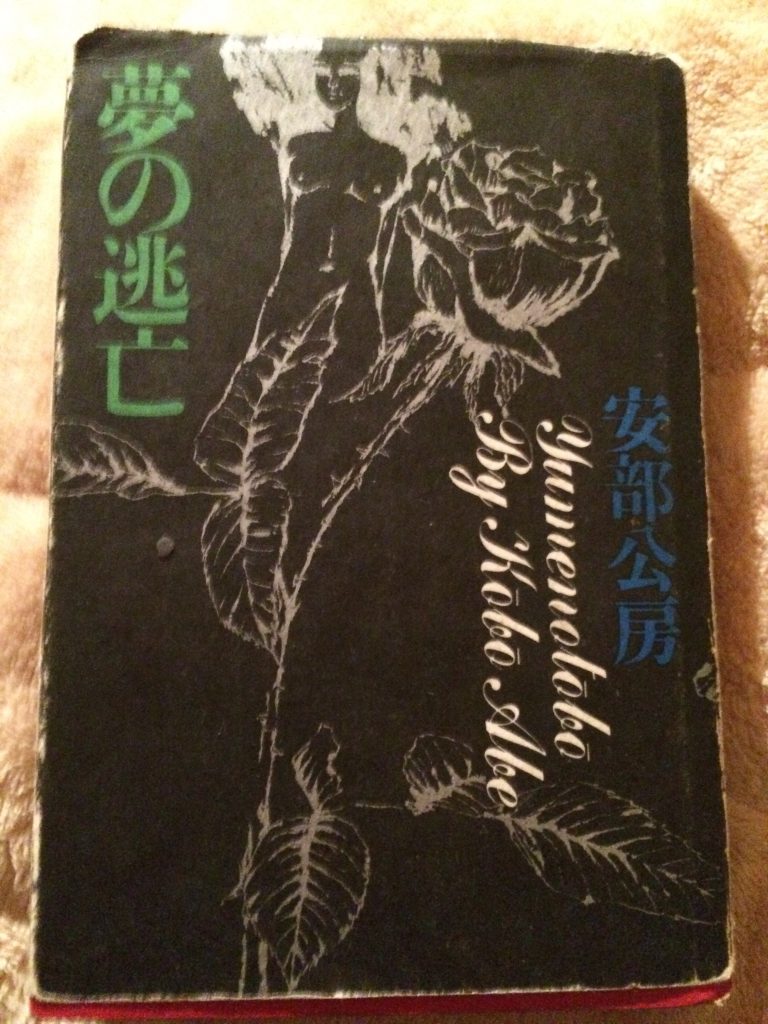岐阜に移住して、二年と半年になる。19歳まで沖縄で過ごし、大学進学のために大阪へ出て、東京で二年間働いていた。沖縄にいる頃も、大阪でも、東京でも、まさか自分が岐阜で古本屋をはじめるなんて、これっぽっちも考えていなかった。
特に大きな目的はなかったけれど、新卒で入ったのはイベントを企画するあまり大きくない会社だった。どうやって入りたい会社を選べばいいのか悩んだ結果、女性社員の肌ツヤが良くて、一人でなんでもこなせる会社を選んだ。心のどこかで、いつか自分で何かをしよう、と思っていたけれど、一体何をしたいのかは皆目わからなかった。
東京での生活は楽しかった。誰も私のことを知らないまっさらな土地は新鮮で開放感があった。好きなことを好き、と自信を持って言えるようになった。美術館も大きな本屋はいつでも魅力的だった。それでも、満員電車はいつまで経っても慣れることができなかったし、新宿も渋谷も怖かった。働いている頃、休日は自転車に乗って公園に行って本を読むことが楽しみだった。通勤の電車の中で、よしもとばなな『キッチン』を読んで涙が止まらなくなったとき、そろそろ東京で過ごすのも潮時かもしれない、とうっすら感じていた。
そんなときに出会ったのが、今の夫である百瀬だった。彼の実家は山に囲まれている小さな街だった。ここに住めば良く息ができるような気がした。まるで映画の中のワンシーンのように恵那駅前を眺めていた。彼と一緒にここで過ごしていくことは夢のように思えて、何も持たずに私は美しい山に囲まれた岐阜へ引っ越して来た。
◎他の記事はこちら
【素描第一回】本は新しい世界への扉
【素描第二回】幼き日の羅針盤『精霊の守り人』
【素描第三回】たったひとつの『声』
【素描第四回】岐阜に移住したときのこと
【素描第五回】無職の側には美しい山と稲穂があった
【素描第六回】好きなことを仕事にしたいわけではなかった
【素描第七回】出張古本屋として活動していた頃のこと
【素描第八回】生きにくかったあの頃の私へ
【素描第九回】理想郷なんてどこにもないから