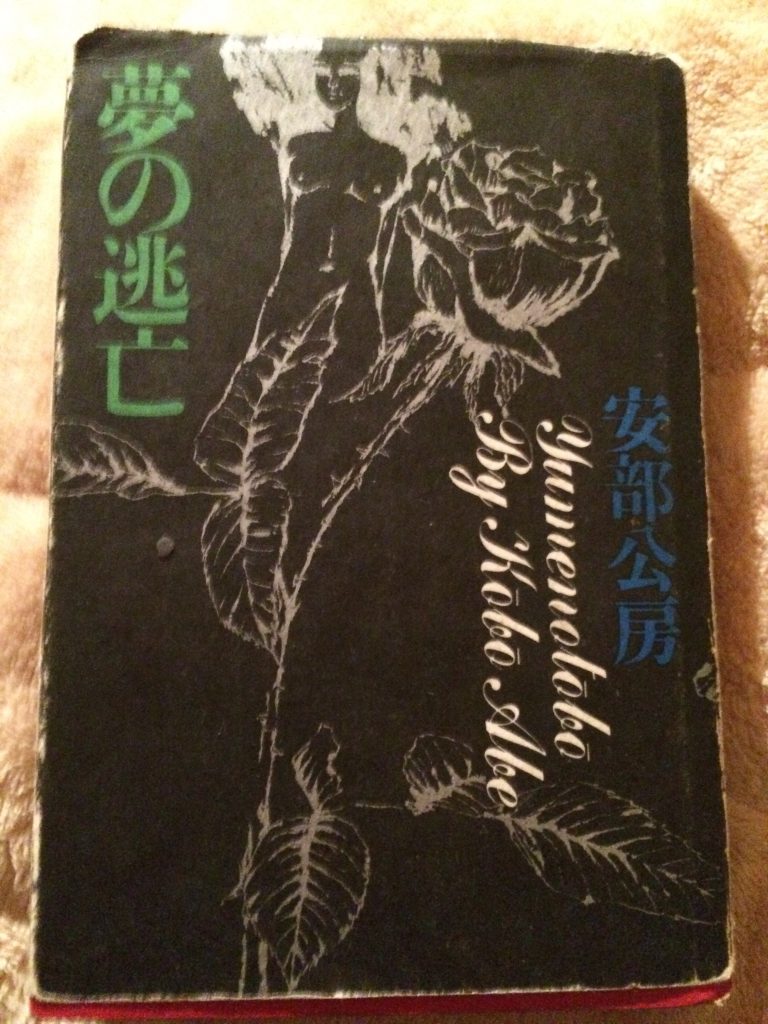平日は市役所で移住相談や空き家バンクの相談を受け、土日は出張古本屋として働く日々が始まった。月に一回、軽自動車に本を詰め込み、一時間半以上かけて設営をし、残った本はまた車に積んで持って帰る。本というのはとてつもなく重たい物体で、イベントの次の日はいつも筋肉痛になった。2人がかりでイベントに臨んで、手元に残るお金は1万円ちょっと。どう考えてもわりに合ってはいなかったけれど、彼と二人で何かをするのは愉快だった。
出張古本屋をしていく中でたくさんの人と出会うことができた。あたたかい視線を投げてくれる人がいる一方で、本に興味がない人もたくさんいた。それで良かった。全て人が「いいね」ということをやることはできない。ほんの一握りの人にとって、心を打つ仕事をしたいと思った。
恵那に引っ越して来てから「何もないところによく来たね」とよく声をかけられた。美しい山々と光る川と多くの人の手によって守られている田園風景を、何もないと思うことはできなかった。もしお店を持つのなら、本や人だけでなく、恵那の美しい自然と静かに会える、そんな場所にしよう、と思っていた。
収益だけを考えるのならお店を開かず、ネットだけで本を売る方がずっと儲かるだろうことはわかっていた。それでもこの場所に一息つけるお店を作りたかった。それは私たちを含めて、田舎に住む誰かを生きやすくするだろう、という根拠のない確信を持っていた。
そんな風に出張古本屋をして半年後、一年前に出会った古民家を借りる方向で話が進んでいくこととなった。
◎他の記事はこちら
【素描第一回】本は新しい世界への扉
【素描第二回】幼き日の羅針盤『精霊の守り人』
【素描第三回】たったひとつの『声』
【素描第四回】岐阜に移住したときのこと
【素描第五回】無職の側には美しい山と稲穂があった
【素描第六回】好きなことを仕事にしたいわけではなかった
【素描第七回】出張古本屋として活動していた頃のこと
【素描第八回】生きにくかったあの頃の私へ
【素描第九回】理想郷なんてどこにもないから